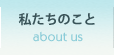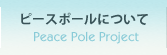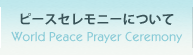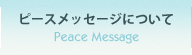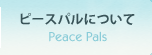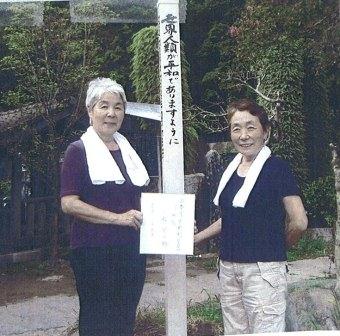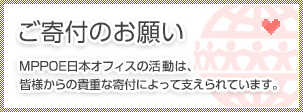社会福祉法人「静和会」にピースポール建立
カテゴリー:ピースポール
2013年1月17日、宮城県の南、亘理郡山元町にピースポールを建てることが出来ました。山元町は総面積の40パーセントが津波を被り、家々はもとより、学校、公共施設、田畑、特産品のいちご栽培のハウス、漁船や漁業の施設などが甚大な被害を受けました。また、町の社会福祉法人「静和会」の福祉施設5つのうち2つが流され、高台への避難を繰り返しているさなか、69名の老人たちと、職員25名が亡くなりました。一時は法人の存続も危ぶまれましたが、現在は職員たちが奮起して再建に励んでいます。
前会長の後を引き継いだ弟さんにピースポールの話をして、役員会に掛けてもらったところ、せつかく建てていただくのなら、日立つ所にお願いしますというお返事をいただき、丘の上にある「静和会」の事務所と並んだ特別養護老人ホーム「みやま荘」の玄関前に建てました。そこでは現在、80人のご老人たちが暮らしています。
思えば、あの大災害の当日、自分の家も流され、身内や職場の仲間を喪うという不幸に見舞われ、精神的に打ちのめされて、仕事を辞めようかと申し出た職員も何人かいたそうですが、皆さん踏みとどまってくださいました。
お会いした時、介護や障害者のお世話に専念していらっしゃったスタッフの方はみな優しく、清々しいお顔でした。ポールを立てる穴を黙々と掘ってくれた若い男性職員の一人は、当日大津波に巻き込まれ、九死に一生を得たそうです。きっと「静和会」の将来を担って立つ一人になられる方だと思いました。作業が終わってから、ピースポールの前でみんな晴れやかな様子で集合写真を撮りました。その日は朝から清々しい雪が降り続いていました。奇しくも、十年前に阪神淡路大震災が起きた日でもありました。手伝っていただいた方々に感謝いっぱいです。(瀬戸多鶴子)
昭和29年(1954年)4月から6年間、私は宮城県桃生郡大川村立大川中学校に教師として勤務させていただきました。現在は石巻市に合併されています。海の恵み、山の恵み、田畑も広がつていて、のどかな村でした。東北一の大河北上川の分流の追波川(おっぱがわ)がゆったりと流れ、延々と続く大堤防の上が東西を貫く幹線道路になっていました。町はその内側に出来たのでした。
2011年3月11日、マグニチュード9.0の地震で生じた大津波は、海沿いの二つの部落を壊滅に追い込み、更に大河を逆流して、打口から約5キロの地点で大堤防を破壊し、山にぶつかつた奔流は渦を巻いて中間の地域を呑み込みました。中心市街地は釜谷といい、山と堤防に囲まれていたために津波の襲来に気付かず、住民の四割にあたる百八十九名が犠牲となりました。大川小学校はそこにあり、百八名のうち74名の児童が亡くなりました。教師も12名のうち10名が亡くなっています。中学校は少し離れていましたが、形だけ残り、今年2月で廃校です。その悲惨な状況を知った直後から、私はこの大川地区に「癒しと希望」の光を降ろそうと思い、ピースポールを建てたいと強く願いました。
願いが叶ったのは翌年の秋でした。二〇一二年、古希を迎えた教え子たちの同期会が松島であり、そこに招かれた私は、我が家の庭のピースポールの写真と、「平和の創造」を数冊持参して話をしました。ピースポールが素晴らしいものだということは、みなわかってくれましたが、川の流域全体が地盤沈下して、どのように修復するのかまだ案が固まっていないので、大川小の傍はまだ早いということで、地域の東端にある尾崎(おのさき)の山の中腹に建てることにしました。今は穏やかに凪いでいる広い長面湾(ながつらわん)を見下ろす場所で、外海は大平洋です。54年前の教え子、浜畑吉弘さんの実家の裏山でした。そこに財団の仲間四人で行きました。浜畑家も津波が貫流し屋根と柱だけが残り、ブルーシートで囲って、彼はそこを作業場にしていました。
毎日、何キロも離れた仮設住宅からバイクで通っては裏山を開墾して公園を造っているのでした。これから生まれてくる子供たちの憩いの広場にしたいのだそうです。彼は若い頃、父親と折り合いが悪くて家をとび出し、遠洋のマグロ漁船に乗り、ブラジルのアマゾン流域で20年間開拓の仕事をして帰国し、今は茨城に家族がいるのですが、家督を継いでいてくれた弟を励ますためにも、単身引っ越してきて、去年の秋から故郷の山を一人で切り拓いているのでした。小柄ながら力仕事に慣れている彼は、2メートル余りもあるピースポールを一人で担ぎ、急な山道をひょいひょいと登っていくのでした。その山を取り囲むように60戸もあつた集落はことごとく廃屋で、時折、土木作業をするために往き来する車の他は人の気配は全くなくて、地盤沈下で広がつた海の水がひたひたと打ち寄せる音だけが聞こえ、小春日和の太陽が反射する小波の上には数羽の白鳥がゆったりと羽を休めていました。
「インターナショナルなものにしたい」という彼の要望で、ピースポールは日本語と英語と中国語、そしてスペイン語で表示しました。彼は、あの大川小学校までハイヒールを履いてでも行けるような遊歩道を造りたいとか、公園を桜の名所にしたいとか大きな夢を語ってくれました。70歳の彼は「必ず、後を引き継いでくれる者がいると信じてます」と語っていました。日が暮れても困らないように、家の外には小型の太陽光発電の蓄電盤が置いてありました。あるNPOから寄贈された物でした。帰りに、もう一度仰ぎ見ると、山の中腹に建ったばかりのピースポールが白く輝いていました。二月半ばになって、そのピースポールの周りの薮椿の花が咲きはじめ、彼の実家の庭に一本だけ生き残ってくれていた梅の木の蕾も綻びはじめたといううれしい電話がありました。(東北ピースポール70本プロジェクトの一環として)(瀬戸多鶴子 記)
東京都昭島市の自宅にピースポール建立
カテゴリー:ピースポール
2013年3月8日、東京都昭島市の自宅にピースポールを建立しました。妻の祖国中国を意識して、中国語を入れて、仲間と一緒に行いました。(薬袋藤夫 記)
名古屋市の徳重熊野社にピースポール建立
カテゴリー:ピースポール
2013年3月23日、名古屋市緑区の徳重熊野社に、氏子総代の方のご協力を得て、ピースポールを建立しました。広大な敷地は自然林に囲んれ、長い参道を登った先に正殿があります。氏子総代の方4名他、12名で行いました。(佐々木公子 記)
愛知県東郷町の富士浅間神社にピースポール建立
カテゴリー:ピースポール
2013年1月10日、愛知県東郷町の富士浅間神社にピースポールを建立しました。敷地は15,000坪あります。県立東郷高校に隣接した平和の礎の石碑の横です。宮司さんが平和を願うのに一番ふさわしい場所を選んでくださいました。東郷町はブラジル人が多く住んでいるので、ポルトガル語を入れました。四季桜が咲く中、13名が参加しました。(小川ちゑ子 記)
愛知県の御嶽(オンタケ)神社にピースポール
カテゴリー:ピースポール
2013年4月19日、先達の近藤栄一さんの協力を得て、愛知県御嶽山、東郷町の諸輪御嶽神社にピースポールを建立しました。弘法大師も祀ってあり、神仏混淆の歴史があるようです。新緑美しい中、グループ14名で行いました。(小川ちゑ子 記)
2012年12月中旬から南半球をピースボート(船)で回る計画を立てていたところ、子どもたちにピースポールに絵を描いてもらい、建立するプロジェクトがあると知りました。(アート・ピースポール・プロジェクト)これはWPPSニューヨークオフィスを中心に進められているプログラムで、アメリカ国外で行われるのは初めての試みだそうです。
ぜひ、ピースボートの寄港地で現地の子どもたちとやってみたいと思い、WPPS日本オフィスの担当の方々に、現地受け入れ先などを相談しました。
ピースボートの船旅で地球を3分の2ぐらい周った2013年2月14日、船内で募った参加者20名(日本19、スペイン1)とチリの現地コーディネーター"サークロ・アレフ"のセルヒオさんの案内の下、バルパライソ市でコミュニティ活動を行っているコロディジェーラを訪れ、子どもたちとピースポールに絵を描き、ごらんのとおりのカラフルでユニークなピースポールが出来ました。地域のボーイスカウトの青年たちの協力で、それを同センターに建立しました。また南米の輝ける太陽の下で、スカウトの青年たちを中心に、みんなでフラッグセレモニーを行いました。みんなで心を一つにして、とても美しいセレモニーでした。
参加者20名は今回初めてピースポールを知り、フラッグセレモニーにも参加し、よい体験をした!感動をした!この活動はすばらしい!とおっしゃってくださいました。万歳!(山下いづみ)
2013年5月7日、徳島市の護国神社にピースポールが建立されました。ここには、戊辰戦争から第二次大戦に至る事変・戦争等の国難に準じた徳島県出身の英霊三万四千三百余柱を祀られています。桑内さんのご尽力でした。(林岩夫)
2013年5月7日、桑内さんのご尽力で、徳島市内の事代主神社にピースポールが建立されました。事代主神社は、1月のえびす祭りえべっさんが有名です。(林岩夫)
宮城県石巻市の多福院にピースポール建立
カテゴリー:ピースポール
2012年9月5日、宮城県石巻市の多福院境内にピースポールを建立しました。東日本大震災で津波の大被災を受け、この地域は石巻でも最も被災が大きかった場所です。ご住職は、「今、みんなが望んでいる平和を、このような形で身近に建ててもらって、とてもうれしい。必ず復興します」とお話くださいました。このピースポールは、小野寺昌子様、田中智子様のご尽力で建てられたものです。(東北70本プロジェクト)(和泉日出子)